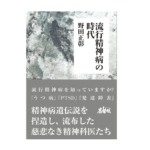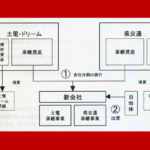長崎市の高校生が自殺した問題を追う若い共同通信記者が、共同通信を辞めざるを得なくなった。『記者迫害―崩れゆくジャーナリズムの現場から』にはその経緯が淡々と書かれている。抑えきれない「怒り」を抑えつつ、「記録し表に出す」ことに重きを置いた本だといえる。(依光隆明)

2022年11月に文芸春秋から出版された『いじめの聖域』
発端は『いじめの聖域』
著者の石川陽一氏は1994年生まれ。早稲田大学を卒業後、共同通信に入社する。最初の赴任地が福岡、次の赴任地が長崎だった。私立長崎海星高校進学クラスの2年生だった福浦勇斗君(16)=仮名=の自殺問題にかかわったのは長崎支局にいたときだ。2017年4月20日、勇斗君は下校途中に自宅近くの公園で命を絶った。遺書が残され、そこには「そういうこと」が原因だった旨がかかれていた。父親は49歳、母親は45歳。勇斗君は物静かな優等生だった。絵に描いたように平凡で幸せな家庭は一瞬にして崩壊した。「そういうこと」とは何なのか。絶望と混乱の中、両親はそれが「いじめ」であったことを知る。
この問題が特異なのは長崎海星高校が自ら設置した第三者委員会の結論を拒否したことだ。有識者5人の第三者委員会は、1年4カ月後に「自殺の主要な原因はいじめ」とする報告書を完成させた。ところが学校は報告書の受け取り拒否。加えて日本スポーツ振興センターへの災害共済給付金支給申請も拒否する。いじめと結論づけた報告書に納得できないから報告書を添付することができない、だから給付金の申請もできないという論法だった。
両親の思いは「息子の死を再発防止に生かしてほしい」だった。その思いが伝わらないのか、誤解したのか、学校側は第三者委員会拒否、給付金申請も拒否というにわかに信じがたい論理で両親の思いを逆なでする。両親は孤独だった。なぜ?どうして?と疑問が募る両親は、地元メディアの報道にも不信を抱く。唯一、信頼を置くことができた記者が石川氏だった。ただし石川氏がこの問題にかかわり始めたのは勇斗君の死から2年後、第三者委員会報告を学校側が受け取り拒否したあとのことだ。つまりいったん終わった問題を石川氏は取材し直そうとした。丹念に取材する石川氏を信頼し、母親は学校とのやり取りを記録した音声データを字に起こして提供する。石川氏は勤務時間外の時間をも使って地道な取材を続け、千葉支局に異動した後の2022年11月に1冊の単行本を上梓した。タイトルは『いじめの聖域―キリスト教学校の闇に挑んだ両親の全記録―』。副題にある通り、勇斗君の両親の視点で学校側や県教育委員会、さらには地元新聞社の対応を丹念に記している。この本は大宅壮一ノンフィクション賞の最終候補作に選ばれるなど、高く評価された。なにより勇斗君の両親が高く評価してくれた。ところが…。

『記者迫害』。花伝社刊
きっかけは長崎新聞からの抗議
『記者迫害』には、『いじめの聖域』を出して以降に起きたことが記されている。タイトル通り、共同通信社内で石川氏は「迫害」される。つまり石川氏が体験したことを石川氏の目線で記したノンフィクションが『記者迫害』だ。日本を代表する報道機関の中で起きた小さな嵐の記録と言っていい。
最大の問題は、なぜ迫害に至ったか。『記者迫害』を読むと、「迫害」に至るきっかけが長崎新聞社から共同通信への抗議だったことが分かる。『いじめの聖域』に長崎新聞の批判めいたことが書かれているという抗議だ。長崎新聞の抗議が激しかったからなのか、共同通信は石川氏を査問し、『いじめの聖域』の重版差し止めまで命じる。『いじめの聖域』を出版したのは文芸春秋だ。文芸春秋という巨大な存在には何もモノ申さず、共同通信は自社の社員である石川氏に重版差し止めを命じた。共同通信は出版契約にかかわっていないのだから、重版差し止めを命じる権限はない。石川氏が事実誤認を書いたわけでもない。査問の末に共同通信が石川氏を指弾し得たのは長崎新聞に直接取材していないという一点だった。言いがかりのような理由で2023年4月に石川氏は記者職を外され、同年7月に共同通信を退職する。
共同通信の経営は全国の加盟社(全国の地方紙やNHK)が納める社費で成り立っている。加盟社に頭が上がらない構図は想像できるとしても、『記者迫害』に記された共同通信幹部の言動はその想像を超える。その意味では『記者迫害』は共同通信という村社会の貴重な記録でもある。ただし報道機関の内幕を生々しく記した内容が内容だけに、主要メディアにこの本の書評が載ることはない。花伝社刊。税別2000円。
共同通信退職後の2023年8月、石川氏は東洋経済新報社に記者として再就職した。その直前、石川氏は共同通信を相手取って表現の自由をめぐる民事訴訟を起こしている。東京地裁での公判は2025年12月5日に結審、2026年2月に判決が下る。




-1-150x150.jpg)