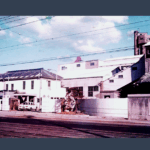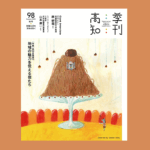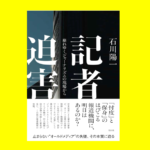災害が起きるたび、避難所の重要性がクローズアップされる。2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県名取市閖上(ゆりあげ)地区の町内会長、長沼俊幸さん(62)は静岡県浜松市の防災学習講座に登壇、避難所での体験を語った。東日本大震災のとき、避難所では家族の居場所を守る段ボールの仕切りさえなかったこと。昨年の能登半島地震の被災地でも同様だったこと。問題が行政に検証、共有されぬまま繰り返されてきたのでは、と。(寺島英弥)
=2025年7月26日、浜松市防災学習センター(提供写真)1.jpg)
被災後の避難所の生活を語る長沼さん(右上の右側)=2025年7月26日、浜松市防災学習センター。提供写真
静岡県浜松市防災学習センターが2018年12月から毎月催している講座。東海地震、南海トラフ地震への備え、災害被災地へのボランティア支援が盛んな土地柄もあり、東日本大震災の当事者らも招かれる講座には大勢の市民、遠来の聴講者が集う。7月26日にあった今回の講座は、「『復興』とは何か 閖上が見つめた震災14年の軌跡」と題し、6500人の住民のうち死者が750人、不明者38人に上った閖上地区の被災とその後の歩みを、自身も被災者の長沼さんが語った(寺島が聴き手)。

震災前の閖上地区。東日本大震災後、地区の高台に立てられた掲示板を複写=2013年11月、依光隆明撮影
津波で2キロ先まで流された
2011年3月11日午後2時46分の大地震を、長沼さんは名取市の内陸の仕事場(水道設備業)で奥さん、長男と三人で被災した。閖上の自宅には両親がおり、長男と一緒に避難させたあと、家の中の様子を見ようと戻った時、道路に黒い水があふれてくるのが見えた。「津波への意識はなかった」と言い、偶然通った消防車の避難の呼び掛けに驚いた(防災無線は鳴らなかった)。奥さんと二階に上がった瞬間、ドーンと衝撃があった。長沼さん夫婦は三階の屋根によじ登り、そのまま津波で2キロ先まで流されて九死に一生を得た。

「地震があったら津波の用心」と昭和三陸津波の教訓を刻む震嘯記念の碑=名取市閖上、寺島英弥撮影
津波の伝承が忘れられていた
約6500人が暮らした閖上でなぜ、800人近くも犠牲になったか。「ここは津波が来ない町だ」と誰も疑わなかったと長沼さん。写真で見せたのが、いまも残る高さ2メートル近い震嘯記念の碑だ。「地震があったら津波の用心」の標語と、昭和8(1933)年3月3日の昭和三陸大津波の事実を刻む。「子どものころ登って遊んだものだが、何の碑か知らず、津波は来ないと両親も言っていた。昭和7年生まれの父も、近隣の高齢者たちも津波を覚えておらず、遠くの牡鹿半島(三陸海岸の南端・石巻市)が津波を弱めてくれる、と信じていた」。旧閖上町設置の津波到達点の標柱も現存するが、人から人への伝承はなく、いざ津波が来ても、どんなものか、どうすればよいか、誰も分からなかったという。
「私は、閖上を訪れる人たち、若者たちを必ず石碑に案内し、伝承がなされないとどうなるのか話している。浜松にも、先人が災害の記憶を伝えた場所が必ずあるはずだ」

震災直後の閖上地区。住宅地ごと津波で流された。瓦礫すらほとんど残っていない=2011年3月27日、依光撮影
仕切りなき避難所のストレス
九死に一生を得たあと、無事だった家族と避難所(市内の学校体育館)に入った。その時を思い起こさせたのが、昨年5月中旬にボランティアとして訪ねた能登半島・珠洲市の小学校の避難所だった。体育館に段ボールで仕切られた避難者、家族の居場所が並び、段ボールベッドもあった。最低限過ごせる様子だったが、話を聞くと、昨年1月1日の大地震発生後、しばらく仕切りはなかった。真冬の能登の避難所から被災者の不便、不満を伝えた報道の結果、仕切りが入るようになり、支援する団体や個人、メーカーなどから提供されるようになった。長沼さんはボランティア先で「5月になって届いた」との話を聞いた。
長沼さんが「ついたての問題」として振り返ったのは、体育館の冷たい床を家族と布団の上で辛抱していた2011年5月中旬ごろ。役員だった長沼さんに、たまたま他所の避難所に行ってきた入所者が「段ボールの仕切りがあった」と伝えた。驚いて、すぐその日に関係者の会議を開いて市の担当者に問うと、返答は「あれ、役所の体育館にいっぱいありますよ。皆さんから要望されませんでしたので」。津波ですべてを流された境遇の被災者と日々接している立場とは思えぬ発言に、長沼さんは「ふざけんなよ!と、滅茶苦茶に怒った」。
避難所は「平常の場」ではなかったという。「仕切りがないと、いつも他者の目にさらされ、すごいストレスになった。それが溜まると、人間、どうなると思いますか?」と、長沼さんは参加者に問いかけた。「つい昨日まで❝一緒に頑張ろう❞と言った人が変わり、攻撃的になる。そんな人が多かった。受け入れがたい現実、先が見えない不安、いつも同じ食事への不満。それを皆、我慢していた。身内が安否不明の人、線香を手向けたばかりの人もいるのだから。私もまた普通の状態でなかった。心の助けが一番必要な時、場所なのに」

震災から半月後の閖上中学校。建物自体は無事だった=2011年3月27日、依光撮影
それでも新しい絆を
そんな「負」の経験が、なぜ記録されず、生かされず、「次の被災地」でも繰り返されてきたのか―。そこに長沼さんの大きな疑問があるという。「被災者はただ耐えることを強いられ、その日々もすぐに忘れられる。被災者と向き合った行政がさまざまな問題を検証し、全国の自治体が共有し継承すれば、被災者支援の在り方も改善できたはず」。阪神淡路大震災から数えても30年。『孤独死』の問題も含めて、いまだに被災者は救われていない。
閖上地区の「復興達成宣言」のイベントを、名取市長が大々的に催したのが2020年3月30日だった。「街の半分は空き地で、道路は土の状態だった」が、市は成果を急いだ。前年に発足した閖上中央町内会の会長に選ばれた長沼さんら、住民は「『復興』の言葉にびっくりした」。自身は避難所生活のあと、仮設住宅で世話役として6年を過ごし、再び集って入居した閖上の仲間と和やかな支え合いの絆を育てた。「内陸のどこかに、昔なじみの人たちとまた『小さな閖上』をつくって一緒に暮せれば、復興だと思っていた」。それが夢だったという。
もともと閖上の住民は、約7割が津波の恐怖などから「移転したい」と希望した。が、市は400年の歴史ある漁港の名を惜しんだか、他の被災地に例のない「現地再建」の方針を推し進め、帰還者は150世帯ほどに減った。「そこで私の『復興』はなくなった」と長沼さんは振り返った。住民たちは津波で古いコミュニティーを壊され、仮設住宅で絆を取り戻したが、帰還をめぐってまた辛い選択を強いられた。8棟の新しい公営アパートも市が「公平の原則」からクジ引きの入居を採り、独居や老夫婦の世帯は孤立の不安を抱えた。津波を知らない若い新住民も増え、その融合が長沼さんら中央町内会の役目になった。
-1-1024x647.jpg)
現地再建された閖上の街を望み、地元の尚絅学院大生と話す長沼さん=2023年10月21日、寺島撮影
薄れゆく古里の記憶
「コミュニティーは一日でできない」と長沼さん。年配の住民を誘う「お茶会」を毎月催し、子どもや若い親も交流を楽しめる祭りを企画し、顔を合わせる人には声を掛けてきた。新しい観光施設も遠来の客でにぎわい、毎年3月11日の慰霊祭は懐かしい仲間との再会の場になる。そして、来年は震災からもう15年―。だが、と長沼さんは語った。「年を経るごとに、子どもの頃の町の風景が思い出せなくなり、寂しさが増す。それも震災というものの一つ」。埋めがたい古里喪失の傷みとともに、こう思う。「復興とは何なのか。機会があるごとに人に問うてきたが、誰も答えられない。私は、復興という言葉が嫌いです」
-1-1024x768.jpg)
津波から1年半後の閖上の風景=2012年9月20日、寺島撮影

-1-660x400.jpg)