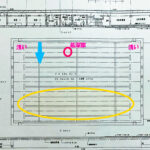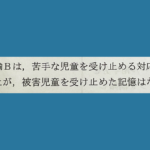1971年の「生コン事件」当時に東大助手だった宇井純さん(1932~2006)は、自主講座「公害原論」で全国的に知られていた。宇井さんが1997年に発表した論考「高知パルプ生コン事件」は高知ローカルにとどまらない視座を備えている。重要な論考なので、できるだけ原文を生かしながら紹介する。(依光隆明)

高知パルプが操業していた時代の近隣工場。お隣さん的な製紙工場だけでも4社あった=「浦戸湾を守る会」事務局長、田中正晴さんの持つ資料より
日常雑貨用ちり紙等で全国一位に
宇井さんの論考は、高知県を紹介するところから展開する。
〈高知県は四国の南岸にあり、工業化の遅れた伝統的な農林漁業の第一次産業を中心とする地域である。しかし温暖な気候と豊富な降雨量(4000mm/年)、長い海岸線によって、第一次産業の生産性は高い一方で、台風・地震・津波等の天災の被害の多い不安定な条件も持っている。この風土のもとで山野に自生する植物の繊維を用いる独特の伝統産業としての和紙生産が、徳川時代から有名であった。洋紙技術の導入を経てそこから発展した中小製紙業は、豊富な水を利用して第二次大戦前には日常雑貨用ちり紙等の生産地として全国的にも第一位を占めた。この紙製品は農業にも応用され、保温苗床、次いでビニールハウス農業などの新しい技術の出発点にもなった〉
製紙が県の伝統産業だったということだ。県庁所在地の高知にも製紙工場は少なくなかった。「浦戸湾を守る会」が発行した『高知生コン事件の全貌』(和田幸雄著)によると、高知パルプができた場所にはもともと科学加工紙株式会社の工場が立地していた。1973年3月に行われた生コン裁判の被告側冒頭陳述では、高知パルプがあった高知市旭町にはほかに「河野製紙」「ニッポン高度紙工業」「南海製紙」「金星製紙」「三好製紙」「鷹城製紙」「御荘ろ紙」が「集中して存在」したと指摘している。
論考は住民気質や自然条件へと進む。
〈政治的にもこの地域の住民は進取の気象に富み、明治維新の原動力となった青年下級武士グループを生む一方で、自由民権運動の中で活躍した人材も多い。また北米・南米等への海外移民も多かった。高知市は高知県の中央部にある政治中心で、東西に走る丘陵地の間の狭い入江の奥にある広い沼地が、河川の運ぶ土砂によって埋められて沖積平野化し、さらに人為的な干拓が進められた結果として残された浦戸湾の奥に立地した都市である。浦戸湾は世界第二位といわれた豊富な魚種と、その変化に富んだ美しい風景によって、長く高知市民の庭として親しまれてきた〉
「世界第二位といわれた豊富な魚種」とは高知大教授の蒲原稔治博士が調べた194種のことだろう。以上を前振りとして、宇井さんは公害の発端へと切り込んでいく。パルプ工場がなぜ立地したのか、ということだ。

1962年1月23日の高知新聞。パルプ工場ができて以降、高知市の江ノ口川は一気に汚染が進んだ。魚が泳ぐ「川」から人が近づかない「どぶ」へと変わり、家庭ごみまで捨てられるようになっていた
県の悲願だったパルプ工場
〈豊かな第一次産業の存在と、中央消費地からの距離が、高知県の工業化が遅れた原因である。高知市の浦戸湾岸に、第二次大戦前に立地した豊富な石灰岩や水力発電を利用した日本セメント、東洋電化、宇治電化学などのいわゆる港六社があったほかは、これといって大きな工場は県内に存在しなかった。この中で豊富な木材を国内他地域に輸出し、パルプを輸入して紙を抄き、加工する製紙業の構造を改善するために、パルプ工場を作る試みは戦前からあったが、1930年代には一度操業を開始したパルプ工場が、排水による被害に憤激した農漁民の抗議で操業を中止し挫折している。第二次大戦後、消費物資の極度の不足から、地方産業として製紙業がパルプを自給する体制の確立が挙県的課題とされるに到った。他方で過去にパルプ排水による被害の経験を持つだけでなく、現に製紙業の排水によっても被害を受けている農漁民がパルプ工場の立地に反対することも必然的に予想された〉
パルプというのは製紙用の原料繊維(パルプスラリー)のことで、木材からセルロースを取り出して作る。パルプを原料にして紙を抄いたり加工したりする製紙業が発達したのが高知だが、木材供給県にもかかわらず肝心のパルプ工場がない。パルプ工場には潤沢な資金と用地が欠かせないからだ。パルプ工場の立地は、いわば県の悲願だった。
〈1948年5月に高知市の有力な製紙業者・高知製紙から亜硫酸パルプ工場の設置認可申請が高知市に提出されると、製紙業と農漁業の対立は一気に表面化した。県知事・市長・県市議会議長らの政治指導者は第二次産業振興の経済的見地からパルプ工場建設計画を支持し、地域住民と漁民は生活体験から猛烈な反対を展開した。申請が提出された高知市だけでなく、高知県中西部の林産中心・窪川町での議会が工場誘致を決議し、下流の大正町は反対を決議した。窪川町と高知市の中間に位置する須崎町でもこの時期工場誘致を決議している。高知市の東に位置する日章村は、旧軍飛行場の跡地にこのパルプ工場を誘致しようと村長以下全議員が運動し、一時工場立地が決まりかけるが、漁民・村民の他地域パルプ工場の見学調査などを契機にした反対運動の盛り上がりに、村長・村議会の全員辞職という結果で計画は挫折する〉
工場誘致を進める政治・経済界のリーダーと、住民による反対運動。パルプ工場の立地をめぐり、県内あちこちで対立が起きていた。押さえる必要があるのは、パルプ工場の設置申請が「高知市の有力な製紙業者・高知製紙」から出されたことだ。次回以降で触れるが、当初は地場資本でパルプ工場を造る構想だった。中途で経済的事情から県外資本に任し、そのことが問題を深化させていく。

高知市街。高知城付近から西を見ると、2.5キロほど先に旭町がある。高知パルプの廃液は旭町から江ノ口川を伝って市街中心部へと流れ込んでいた=Google Earthより
最も立地してはいけない場所に…
〈このような各地の工場誘致と反対の盛り上がりのため、工場立地計画は各地を転々とした結果、当初の高知市西郊の旭町にあった製紙工場跡地にパルプ工場を建設することに決定した。企業側は各地域が工場誘致のために互いに競争して提示する条件のうちから最も有利なものを選択して立地を決定することになる。この過程は、高知市の政治経済の有力者の引力が他地域に比して強く、かつ工場立地の直接地元の反対が相対的に弱かったことを反映している。しかしこの立地決定は、公害防止の立場から見れば、各候補地のうちで最も不利な選択となった。周辺はすでに人口の密集地であり、工場敷地は狭く、緩衝地帯や将来拡張の余地もなく、排水処理のための用地も全くとれないことは明らかだった。排水はすでに製紙工場の排水や都市下水で相当に汚染された小さな市内河川・江ノ口川を経由して浦戸湾に流入するので、ここに日産20トンのSPパルプ工場(注・Sulfite Process=亜硫酸法)を建設すれば、大気・水の猛烈な汚染が起こり、深刻な公害が発生することは当然予想された。水汚染については、人口数十万人分の下水に相当する汚染負荷が江ノ口川上流で発生することになる〉
「公害防止の立場から見れば、各候補地のうちで最も不利な選択となった」という指摘は重い。その後の推移は、宇井さんの指摘通りとなった。(つづく)