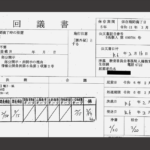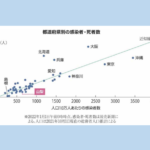高知県や紀伊半島南部と並び、南海トラフ地震で深刻な被害が想定されるのが静岡県だ。静岡県浜松市で続く防災学習講座は、2018(平成30)年12月からほぼ毎月、専門家の話や体験学習だけでなく、東北など全国の被災当事者を講師に招いている。「浜松からも多くの市民が災害支援に参加している。その経験や、現地で培った人の縁も次の学びにつながる」と考えたからだ。講座を企画し、自身も子育て支援NPOの立場から被災地と関わっている原田博子さんに話を聞いた。(寺島英弥)
2025年7月27日、浜松市-1-1024x678.jpg)
「はままつ子育てネットワーク ぴっぴ」のスタッフと原田さん(中央奥)=2025年7月27日、静岡県浜松市
原田さんは浜松市防災学習センター の副センター長で、指定管理者。2004年に「子育てしやすいまちづくりを」を理念として「はままつ子育てネットワークぴっぴ 」(2018年に認定NPO法人、浜松市子育て情報サイト ぴっぴ )を立ち上げ、理事長を務める。東日本大震災を始め、熊本地震、能登半島地震などの災害被災地にも、子育ての視点から支援に携わってきた。

人口77万人の政令指定都市、浜松市。静岡県では最大の人口を擁している=Google Earthより
当事者の声を聴き、現実を知る
――防災学習講座を始めたきっかけは何ですか?
地震などの大きな災害が全国でたび重なっていますが、この浜松市は被害想定が極めて深刻な地域です。南海トラフ地震の津波到達時間は約18分、最大津波高は約15メートルと予想され、近くに原子力発電所(浜岡原発から最短地まで約33キロ)もあります。どうしていいか分からない、という問いに応え、市民の防災の知識を向上させたいという思いが募りました。拠点になる浜松市防災学習センターが開館し(廃校舎を活用)、大学などの専門家を呼んで話を聴き、多世代の人がワークショップをして学ぶ機会を重ねるうち、参加者から「被災地の当事者の声を聴き、現実を知りたい」という声が高まりました。
熊本地震(2016年)の被災地支援に行った市職員やボランティア、支援団体の人たちの現地報告を企画したら、市民の関心とすごく響き合い、備えについての知識が上がっていきました。浜松市から全国の被災地支援に出掛けた人も多く、その経験や生きた情報、人の縁も防災学習講座につながっています。被災地の現状と、さまざまな教訓を「被災」「復興」「防災」の視点で見つめながら、実体験を語ってもらえる当事者の方々を招いています。
2024年4月20日、市防災学習センター.jpg)
能登半島地震の被災地、珠洲市の支援に入った浜松市の保健師、消防士、危機管理課職員に話を聴く原田さん(壇上左端)=2024年4月20日、浜松市防災学習センター
――東日本大震災の被災地からはどんな講師が来られましたか。
宮城県南三陸町志津川病院の医師として被災後も患者を守り続けた菅野武さん(現東北大医学部准教授)。長男の健太さんら同県女川町の七十七銀行支店で多くの行員が亡くなったことへの責任を問い、「企業防災」を訴え続ける田村孝行さん、弘美さん夫妻。570人の小中学生全員が津波を逃れ無事に避難した岩手県釜石市鵜住居の「いのちをつなぐ未来館」職員の菊池のどかさん。元河北新報記者で郷里福島の原発事故被災地などの取材を続ける寺島英弥さん。そして今度初めて登壇いただいた宮城県名取市閖上の町内会長長沼俊幸さん。東北の被災者の法律支援から各地での防災支援へ、活動を続けている静岡市の永野海弁護士…。
浜松や県内から東北へボランティア活動に行ったり、ゲスト講師の方と現地で知り合ったりした人も多く、いつも定員を超える受講申し込みをもらっています。

「つながる支援パック」。乳幼児、アレルギーのある子に必要な食品、用品をひとまとめで手渡せる
「つながる支援パック」の活動から
――原田さん自身が被災地支援で出会い、講座に招いた当事者もおられますか?
私が理事長をしている子育て支援NPO「ぴっぴ」は、「つながる支援パック」を作って熊本地震の被災地や西日本豪雨災害に遭った広島などに届けてきました。これは、乳幼児がいる家庭に必要な支援物資(子ども一人分のミルクや離乳食、紙おむつ、洗浄綿など)をひとまとめにしたセットです。長蛇の列で支援品を待つことなく、またアレルギーへの無理解から子どもを守るためにも、一目で分かるロゴマーク入りのトートバッグに詰めて現地に届けています。
昨年1月に起きた能登半島地震の際、「つながる支援パック」を送らせてもらった石川県珠洲市で、乳幼児がいる避難所などの被災者に渡してくれたのが、市健康増進センター所長だった三上豊子さん(現健康サポート推進室長)でした。その縁から、保健福祉の最前線での苦心と「復興」への思いを、浜松にお招きして語ってもらいます(9月28日に講座)。そして、やはり能登で知り合ったNPO法人日本レスキュー協会の辻本郁美さん。珠洲市でペット世帯専用避難所の開設に携わり、「ペットと安全に避難することは、家族全員の命を守ること」、「飼い主の被災後の生活、心のケアにつながる」と日常からの対策、訓練の大切さを語ってくれました。
と未就園児の親子、支援員たち=2016年5月、熊本県嘉島町-1-1024x688.jpg)
熊本地震の際、「つながる支援パック」などを届けた原田さん(手前左端)と未就園児の親子、支援員たち=2016年5月、熊本県嘉島町
多様な担い手と仲間に、共に被災地に駆けつける
――当事者や支援の担い手との出会いから全国の被災地とつながる、と。
静岡県ではボランティア協会を中心に毎年、南海トラフ地震の図上訓練を半年かけてやっていました。多様なNPO、団体が集まり、「ぴっぴ」も子育ての分野から参加し、仲良くなり、どこかで災害が起きれば共に被災地支援に駆けつけます。そんな土地柄です。
「ぴっぴ」は今年、発足から20年になりますが、私たちなりの問題意識で防災に取り組んできました。例えば静岡では9月1日と12月1日(県独自の地域防災の日)に防災訓練があります。浜松は地域のつながりが強く、自治体加入率は95%。伝統の「浜松まつり」にも町内単位で参加します。だから防災訓練も大勢の市民が参加しますが、出られるのは男性たち。乳幼児を持つ母親たちはなかなか出られません。そこで私たち「ぴっぴ」が市の社会福祉協議会や災害支援ボランティアを講師に招き、母親向けの勉強会をやってきました。
支援物資もむだに送れば、積まれるだけで使われません。そんな光景を熊本や東北の被災地で見てきました。それを防ぐため、現地に入っている災害支援の人たちから、何を、どこに、どうやって送ればいいか、詳しい情報をもらったり、届けるのを頼んだりしています。
「つながる支援パック」には地元の浜松医科大学から協力、監修をもらいました。「アトピーがひどくなると皮膚病と周囲から間違われ、迷惑がられた」という避難所の話を聴いて医師に相談すると、ワセリンが肌に良いと教えられ、熊本地震の時から支援パックに入れて送っています。人のつながりこそ、次の災害支援の力になります。