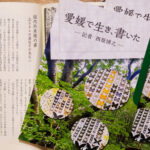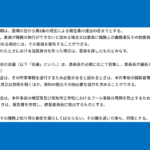高知県の最東端、東洋町には「こけら寿司」と呼ばれる押しずしがある。江戸時代からあった伝統料理で、ハレの料理として受け継がれてきた。ところが過疎化の波はハレの場を減らし、こけら寿司の出番も減っていくばかり。ハレの場を彩る本来のこけら寿司は絶滅危惧種的な状態に陥っている。東洋町最奥部の真砂瀬(まなごぜ)に、「最後の名人」とも形容される野口登志恵さん(93)を訪ねた。(依光隆明)

こけら寿司と真砂瀬について語ってくれる野口登志恵さん(東洋町真砂瀬)
正月2日に弓を射る
真砂瀬は国道55号を東洋町野根で北に折れ、県道を20分ほどさかのぼった徳島県境近くにある。戦後は30数軒・200人近い集落だったが、今は常に住む人が数軒程度。ただしどの家も手入れが行き届いていて雰囲気は明るい。
野口登志恵さんは昭和7年(1932年)にこの集落で生まれ、集落内で結婚した。真砂瀬については誰よりも詳しい。「(真砂瀬を拓いたのは)もともとは平家の落人なんですよ。山のずっと向こうに弓場の段ってあるんです。そこで弓の稽古をしていたと聞いています」。代々、野口家は真砂瀬の中でも領主的な位置づけだった。「うちに裃(かみしも)があるんですよ。お正月の2日の日に裃を着て田んぼで弓を引きよった。家には刀もどっさりあったの」

野口さんが持つのがこけら寿司用のすし桶。ちょうど1升のコメが入る
コメ1升にユズ2合
かつて野口さんはこけら寿司の普及に努め、こけら寿司を提供するカフェをしたり、「こけら寿司教室」を開いたりもした。こけら寿司普及のリーダー格だった。90歳を過ぎた今、もうほとんどこけら寿司を作っていない。なにせこけら寿司を作るには労力がかかる。手間と時間が欠かせないし、腰を痛めそうになるほど重い重しを載せなくてはならない。一人で作るには体力が要る。
「きょうは朝4時から作りよった」と野口さんが笑う。室戸市の知人の懇請に応え、久方ぶりに作った。作るには、いいサバを入手しないといけない。それを焼き、身をほぐしてユズ酢につける。ユズは高知県東部が全国一の大産地だ。数時間、サバにユズ酢を浸透させたあと、炊き立てご飯にユズ酢ごと混ぜてすし飯にする。野口さんによると、「コメ1升にユズ2合」の割合だとか。きりっとした酸味のユズ香に焼きサバの香りが加わって、なんとも芳醇なすし飯だ。それをヒノキで作った桶に入れる。桶に底はなく、下に敷くヒノキの板が底代わり。ヒノキの板の上に桶を載せ、すし飯を入れる。「ちょうど1升入るの」と野口さん。1升のすし飯を3つに分け、三分の一のすし飯をまず敷いて、味付けしたニンジン、シイタケ、薄焼き卵を載せて彩りをつける。その上にヒノキの板を載せ、同じ要領ですし飯と具材を載せる。3段分ができたらヒノキの板を上に載せ、重しを載せる。6時間ほど置くとすし飯がギュッと締まってこけら寿司の完成だ。なによりその美しさに目をひかれる。純白のすし飯に赤いニンジン、黄色の卵、茶色のシイタケ。3段になって迫力十分。

できたこけらずしを、1段ずつ大きな包丁で3分割
1升で54個のこけら寿司
1段ずつ下ろし、それぞれを丁寧に専用の大きな包丁で切る。まず三つに切り、その一つ一つを六つに切る。つまり1段当たり18個できる。3段だと計54個。つまり1升のコメで54個の小さなこけら寿司ができる。ちょうど手でつまめる大きさだ。ぎゅっと押し固めているのでつまんでもコメがほぐれることはない。口に近づける。ユズの香りが鼻腔を刺激する。いや、身体全体にユズの香りがまとわりつく。口に入れる。ユズ香と、ほんのり焼きサバの香り。甘みもある。おいしい。
「(こけら寿司用の)押し込む桶がうちにあるけんど、ボロボロになっちゅう。何百年もたっちゅうがやないろうかねえ」。野口さんは野口家に嫁入り後にこけら寿司を作り始めた。お祭りごとや祝いがあると総出でこけら寿司を作る。集落中の人が集まり、こけら寿司をつまみながらにぎやかに酒を飲んだ。

真砂瀬の集落から見た風景。山峡を風が吹き抜けていく
「山になってしまうのよ」
「平成10年(1998年)ごろはすごかったよ。ようけ作りましたわ」と野口さんが振り返る。「こけら寿司を大阪の高島屋でも売った。韓国へも持って行って売った」。過疎化の進行とともにこけら寿司のブームは遠のいた。祝いなどハレの場に集落みんなが集まる風景が消え、ハレの料理としてのこけら寿司もほぼ消えた。
真砂瀬は野根川の上流にある。川の水は澄み、山は緑に膨らんで青々としている。しかしその緑が人家に迫っているようにも見えてしまう。野口さんがぽつり。「真砂瀬もなくなるの。山になってしまうのよ」

お皿に載せたこけらずし。1段を3分割し、それを6分割して食べる