「非医療型の子どもホスピス」と聞いて、分かる人がどれくらいいるだろう。概念すらも定まっていないその施設を丹念に取材した『最後の花火―横浜こどもホスピスうみそら物語』が上梓された。「最後」や「ホスピス」という暗いイメージとは対照的に、そこには子どもたちの幸せ感がある。子どもたちに楽しみを与えたいと念じつつ動く人たちの姿がある。(依光隆明)

『最後の花火』。税込み1980円
この「多幸感」はいったい何だろう
著者は2023(令和5)年3月に朝日新聞を辞めた浜田奈美さん。退職後、横浜総局時代に取材した「横浜こどもホスピスうみとそらのおうち(うみそら)」に通って聞き取りを続けた。「ホスピス」から受ける一般的なイメージは、プロローグによっていち早く壊される。印象と現実との違和感は、まず自分自身が受けたのだと浜田さんは明かす。〈うみそらに到着してまだ数時間しか経過していなかったが、私はその場に漂う「多幸感」のような雰囲気に圧倒され、自分の中にこんな「問い」が生じ始めた。厳しい病とともにある子どもたちを中心に成立している場の、この「多幸感」のような空気感は、いったい何だろう――?〉
うみそらに通うたび、浜田さんはその「多幸感」に戸惑うことになる。浜田さんは書く。〈うみそらで繰り広げられている日常は、これまで語られてきた「ホスピス」のイメージとはまったく異なるものだ〉〈とてもシビアな「命の現場」でありながら、絶望や希望といった類の感情ではなく、至高の笑顔を見せてくれる子どもたちの姿に驚き、感動していた。さらに率直に告白するならば、「健康な身体に恵まれて生き長らえながら、漫然と日々を送る我々大人たちの姿と、なんと対照的なことか」ということが衝撃でもあった〉
その違和感をエネルギーに、浜田さんはうみそらをめぐる子どもたちと大人のドラマを丹念に紡いでいく。「うみそら」は医療施設ではなく、建築基準法上は「寄宿舎」。しかしそれが例外というわけではなく、先進地である欧米の子どもホスピスは「教育・遊戯機能をそなえたサナトリウムのような施設」と定義されている。そこには穏やかに死を待つのではなく、精一杯生を楽しんでもらいたいという思想がある。

「うみそら」のホームページ(HP)
病院と自宅の往復だけではいけない
「横浜こどもホスピスうみとそらのおうち」のホームページは、以下のような自己紹介を載せている。
みなさんは「こどもホスピス」という言葉を聞いたことがありますか?
ホスピスと言うと、がん患者さんの病院、というイメージを持つ人もいるかもしれません。
こどもホスピスは違います。病院ではなく、ゆったりと自由に過ごせる「おうち」です。
重い病気をかかえ入退院を繰り返す子どもたちは、健康な子どもたちが当たり前に楽しんでいることを、同じように楽しむことができません。
でも、子どもはいつだって遊びたいし楽しみたい!
学びや遊びや、人との関わりを通して、夢を育み成長するのです。
だから、「横浜こどもホスピス〜うみとそらのおうち」がめざすのは、病気とともにある子どもと家族が一緒に安心して過ごせる場所。
限られた時間であっても、それが永遠に輝く思い出になるような、そんな場所になりたいと思っています。
病気の進行は止められない。しかし病院と自宅を往復するだけの人生でいいのか。子どもはもっと遊びたい。もっと楽しみたい。その願いを、ほんの少しでもかなえたい。実現したい。これが「うみそら」にかかわる大人たちの願いであり、子どもたちは純粋に大人たちの努力を受け入れる。笑顔を見せる。
タイトルにもなっている花火は、本の中で二つ使われている。一つ目は「うみそら」を最初に利用した恵麻ちゃんが2022年夏、6歳で亡くなる直前に手に持って楽しんだ線香花火。もう一つは「うみそら」の近くにある湘南学院中高の協力で実現した。同校の先生の一人が花火師の資格を持っていて、生徒が募金を集めて「うみそら」の子どもと保護者の前で打ち上げ花火を上げたのだ。関東学園大の駐車場から打ち上がる花火に子どもも大人も目を輝かせた。湘南学院の生徒は、花火を見るという当たり前のことが当たり前でない子どもたちの存在を胸に刻んだ。
本物のメリーゴーラウンドを「うみそら」に運び込んだこともある。車いすも乗れるようにしたメリーゴーラウンド。お父さんやお母さんと一緒に乗った子どもたちは、病院や家庭では見せたことのない笑顔を見せた。「たこ焼きパーティー」をしたい子がいればやってみる。雪も持ち込む。もちろん誕生会もやる。病院でも、家庭でもできないことをやってみる。

「うみそら」のHPから
ある看護師の遺贈がきっかけに
「うみそら」は大きな企業や団体の力でできたわけではない。建設に向けて動いたのは6歳の娘さんを脳腫瘍で亡くした田川尚登さん。田川さんを動かしたのは2012年に76歳で亡くなった石川好枝さんだった。独り身だった石川さんは、長年にわたって貯めた遺産の贈り先を探していた。神奈川県内の病院で看護師として働き、キャリアの大半を小児科病棟で過ごした石川さんにとって、忘れられないのは子どもたちのこと。できれば子どもホスピスに遺贈したい旨を弁護士に伝えていた。
「最後の花火」には弁護士の回想と、石川さんの心の中が以下のように描写されている。
〈「勤めていた小児病棟のイベントに、月に一度の『お買い物デー』があったそうです。子どもたちがお小遣いで好きなものを買える日だったそうですが、重度の脳性麻痺のお子さんが床を這うようにして石川さんのところにやって来たので、何かと思ったら、『石川さんに何か買ってあげる』と言って、見上げながらニコニコしていたそうです」
ケアする側とケアされる側。医療従事者として当然と思ってきた立場上の境界線など、邪念のない子どもたちの前ではほぼ無意味なのだった。無邪気な子どもたちからの無意識の「ギフト」に深く癒され、感動した石川さんは、余生を通じて「自分はいったい彼らに何ができたのだろうか」と反芻しているようだった。
そんな石川さんが最も望んでいた遺贈先は「こどもホスピス」だった〉

「うみそら」のHPから
一番の喜びは仲間が亡くならなかったこと
石川さんの遺贈額は1億500万円。託された田川さんは「絶対に子どもホスピスを造る」と決める。横浜市小児ホスピス設立準備委員会ができたのは2014年8月。横浜市は2019年に市有地の30年間無償貸与と年間500万円までの人件費補助を決める。落成は2021年11月だった。1階はカラフルなブランコがあるふれあいスペース、2階は宿泊利用のための寝室3室と大浴場、サウナ。天井の照明は星座になっている。
利用者は、早期の死を免れることができない病気を抱えた子どもたち。病院と家庭の往復ではない第三の場が「うみそら」であり、遊びを楽しむために「うみそら」に来て親子で泊まっていく。容体が悪化したら救急車を呼ぶか、自宅に帰るか。
浜田さんは16歳のチカさんからハッとした言葉を聞く。初めて一家そろって打ち上げ花火を見たあと、穏やかな笑顔でチカさんはこう言った。
「この一年、私が一番うれしいと思うことは、仲間のみんなが誰もいなくならないで生きられているってことなんです。(中略)本当にこの1年間で誰一人亡くならなかった。一番の幸せです」
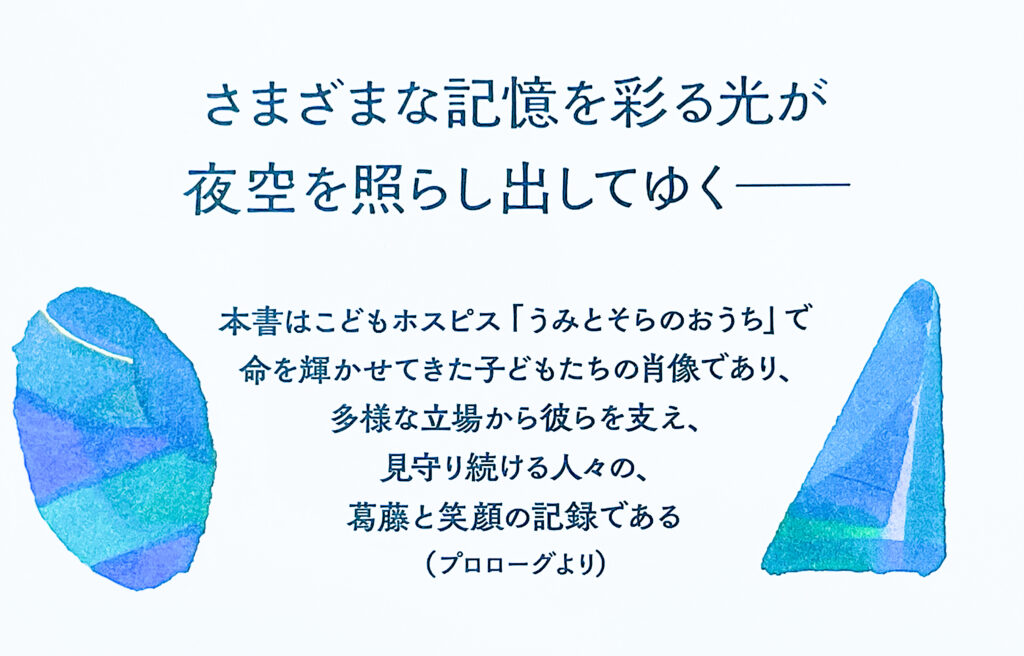
『最後の花火』の裏表紙から
子どもたちの「強さ」を伝えたい
浜田奈美さんは埼玉県出身で、1993年に朝日新聞入社後、1995年から98年にかけて高知支局でも勤務した。エネルギッシュな取材ぶりは当時から目立っていて、高知県内にも知り合いは多い。最後に浜田さんからのメッセージを。
まずは自分にとって「心のふるさと」である高知のみなさんに、
この本についてお知らせさせて頂ける機会を頂き、
とてもとても、とてもうれしく思います。
元「ブンヤ」が、ふうふう言いながら綴ったつたない本ではありますが、
本当に弱い者を真ん中にして生まれた「場」の優しさと純粋さ、
そして真ん中にいる「弱者」のはずの子どもたちの強さとを、
1人でも多くの読者にお伝えしたい・・・と考えながら、書き続けました。
子どもたちの笑顔に思いをはせながら、じっくりお読みいただけると幸いです。

















