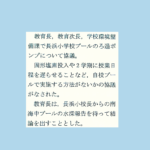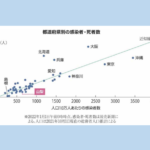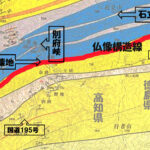映画の黄金期、日本の各地に映画館があった。小さな港町にも、山ひだの中にも映画館があった。娯楽の第一が映画であり、映画が文化だった。当時の雰囲気を今も残す高知県安田町の大心劇場で12月14日と15日、館の誕生70年を祝う映画祭が行われた。(依光隆明)

上映前にちくと一杯。映画×酒=超楽しい
常連さんはビールに紙コップ
初日の14日は午後7時からオールナイトで上映した。山峡の小さな映画館だけに、都市部のシネコンとは映画の楽しみ方が少々違う。シネコンは作品に神経を集中するのだが、今回の映画祭はお酒を飲みながらでも、食事をしながらでもOK。おしゃれな雰囲気もぜんぜんなし。要するに、肩ひじ張らずに映画を楽しんでもらおうというスタイルだ。シネコンで携帯電話の音が鳴ったら大変だが、それもとがめることはしない。もちろん周りに迷惑をかけすぎたらいけないので、声を出すことだけはやめてもらうという程度。このルール、実は映画祭だけではない。大心劇場では普段からおおむねこの通りの運用で上映を続けている。食事をする人のため、最後方にはテーブル席まである。
14日午後6時開場。お客さんが次々と入ってきた。片手に酒瓶をぶら下げて安田駅から約半時間の道のりをブラ歩きしてきた高知市民もいる。常連さんも多いが、遠方から来た映画ファンも少なくない。遠いところでは福島や埼玉からも。常連さんは座席の間に小さなテーブルをセッティング、始まる前から紙コップ持参でビールを楽しんでいる。気がつくと、いつの間にかビールは日本酒に代わっていた。始まるまでまだ時間があるのに。

太平洋側の空から見た安田町。安田川のほとり、山に埋もれるように大心劇場がある=Google Earthより
午後7時、いよいよスタート
太平洋岸を走る国道55号を北に折れ、安田川沿いを約4キロ。大心劇場は山に埋もれるようにたたずんでいる。
70年前の1954(昭和29)年、旧中山村(昭和18年に合併して安田町)の中心部に「中山映劇」として誕生した。いったん廃業を決めたものの、1982(昭和57)に安田川下流の現在地へ建物を移築して復活。そのとき、名を「大心劇場」とした。
現在の館主は、二代目の小松秀吉さん(72)。フォーク歌手「豆電球」として各地のイベントに出かけるし、頼まれれば地域の歌も作る。大心劇場の隣で喫茶「豆でんきゅう」も経営しているので、喫茶店のマスターでもある。加えてもう一つ。プロではないが、映画にもよく出る。たとえば地産地消映画と銘打って制作された全編安田ロケの「追い風ヨーソロ」では制作担当が小松さんのキャラクターに心酔、脚本を書き直して小松さんに出演してもらった。実は50年前の大学卒業時に大映ニューフェイスに合格していたこともあり(結局、映画館を継ぐ方を選んだ)、映画に出るのが嫌いというわけでもない。
午後7時、スタート。大心劇場の座席数は85人で、埋まり具合はその半分ほどか。ビールちびちび、ほろ酔い気味の笑顔も少なくない。舞台に上がった小松さんと奥さんの江利子さんに、東京から駆け付けた「追い風ヨーソロ」の出演メンバーから感謝の花束が渡される。小松さんがお礼の言葉を述べ、長丁場のオールナイト上映がスタートした。

「70周年映画祭」のちらし。実行委員会主催で、両日とも入場料は大人1500円だった
熱いお茶、携帯カイロ、カップ麺
なぜオールナイトか。理由は単純で、酒を飲んでしまったら車で帰れないから。高知行のディーゼルカー(第三セクター「ごめんなはり線」)の最終便も21時過ぎに出てしまう。ならば翌日の朝までのんびり映画を楽しんでもらおうという発想だ。高知行の始発は5時59分安田駅発なので、午前5時を回るまで上映する。時間調整のため、映画と映画の間は1時間近くの間を開けた。間延びするが、星空の下を散歩してもらったり、お茶や酒を飲んでもらったりすればいい。喫茶豆でんきゅうの横にある「焼き肉小屋」(焼肉パーティ用の小屋)でストーブを焚き、そこでお茶を飲めるようにした。携帯カイロも無料サービスし、おなかが減ったときのために各種カップ麺も用意した。
上映するのは大心劇場ゆかりの映画ばかりである。スタートは「旅する映写機」(森田惠子監督)。全国に残る35㍉フィルム上映館を丹念に訪ね歩くドキュメンタリーだ。その中の一つ、現在でも「流し込み」(数巻に分かれた35㍉フィルムを一つの映写機で切れ目なく上映)の手法を残す映画館として大心劇場が出てくる。ほか、福島県に残る歴史的な館や、映画好きの人が作ってしまった新しい館、さらには東日本大震災直後に再開した映画館、移動映写機、映写機再生の職人さん…。小さな館であっても、古い映写機であっても、そこに分厚い歴史が積み重なっていることがよく分ける。ハンセン病施設にあった映写機からは隔離施設の中で映画がどのような位置を占めていたかも語られる。
「旅する映写機」が終わってから次の上映まで約1時間。最初の休憩中にうれしいハプニングがあった。

舞台から会場に声をかける安藤桃子さん。左は実行委員会の桜井珠樹さん
安藤桃子さんが来てくれた!
午後9時半、ラストに予定されている「勝手に流れた星だから」の監督、安藤桃子さんが元気よく現れてくれた。黄色いダウンジャケットがよく似合う。安藤さんは10年ほど前から高知に住んでいて、「勝手に流れた星だから」は大心劇場や安田川上流の馬路村でロケをした。この映画では大心劇場の館主を父親の奥田瑛二さんが務めている。舞台に上がった安藤さんは「時間を作ってなんとか駆けつけることができた」ことを報告。小松さんと掛け合いしたあと、会場を盛り上げて慌ただしく去っていった。
大心劇場にエアコンはない。暖房は数台のファンヒーター頼みなのだが、運の悪いことに14日夜の高知県地方は急激に冷え込んだ。入館者はみんな服を着こんでいる。毛布を持ってきた人もいる。ファンヒーターがフル回転で活躍する。
午後10時、吉田喜重監督(1933~2022)の「幕末に生きる―中岡慎太郎」。1985(昭和60)年、大心劇場を応援しようと地元にシネマクラブができた。全国から映画関係者が大心劇場にやってくるようになり、その中から生まれたのが中岡慎太郎の記録映画を吉田喜重氏で撮るという企画だった。北川村の人たちが中心となって2500万円の資金を集め、映画作りが実現する。当時、吉田氏は巨匠あるいは鬼才と表現できるような遠い存在だった。予想と違い、ロケ隊を率いた吉田監督は気さくだった。夜ごと地元の人と熱く酒を酌み交わし、さまざまな話をしてくれた。いわば地元の人たちとの交歓の中でできたのが「幕末に生きる―中岡慎太郎」だった。

受付に座る「追い風ヨーソロ」の監督兼俳優、大野仁志さん。左のかごは入場者に配るお菓子入れ。お菓子はヨーソロのメンバーが一袋ずつ用意した
「完走者」は17人。平均年齢70歳?
午前0時、「追い風ヨーソロ」。監督兼俳優の大野仁志さんを始め、出演俳優5人全員が東京、横浜、神戸から集合、飛び入り出演した小松秀吉さんを加えた6人が舞台あいさつした。このころになると会場のお客さんの数はかなり減っていた。酔っ払ってしまったのだろうか、快調に飲んでいた人が何人か消えている。予定通りに帰った人、酔って帰った人、睡魔に襲われて帰った人、それぞれの事情で家路についたらしい。
午前2時、スケボー映画3部作「deep in」「よさこい」「へんろ」。これは小松さん夫妻の息子にして大心劇場3代目を継ぐであろう小松健太さん制作の映画だ。舞台そでにスケボーを持ち込み、どのように撮影したかを健太さんが説明してから上映スタート。動きの速い映画だ。スケボーの動きに目を回したのか、酔ったのか、疲れたのか、うとうとする人が多い。眠りこけている人もいる。
午前5時前、遂にラストの「勝手に流れた星だから」。今回の映画祭目玉の一つ、安藤桃子さん監督の小品だ。さすがに観客はみんな起きた。隕石のかけらと馬路村魚梁瀬、そして大心劇場。過去と現在が交差してダムをめぐる物語が紡がれていく。終わったとき、観客から大きな拍手が起きた。
初日の有料入場者数は36人。うち“完走者”17人。まだまだ元気な若者がいる半面、満足に歩けないほど酔った男性もいる。総じて年齢層は高い。完走者の平均年齢は70歳に近いかもしれない。長丁場を完走するうちに仲良くなったのだろう、地元のご婦人が隣席のお客さんに「ちょっとうちで休んで行きなさいよ」と声をかけていた。始発で高知に向かうのは2人。その2人を車に乗せ、スタッフが安田駅に走った。冬の夜は寒くて長い。夜明けまでにはまだ間がありそうだ。

2日目の上映終了直後、館内の様子。初日ほどではないが、おしなべて疲労の色が濃い
フィナーレは豆電球ミニライブ
15日は午後1時から夜にかけての上映だった。この日のラストは「追い風ヨーソロ」。午後8時半に終了後、小松秀吉さんと「ヨーソロ」の出演者が舞台に上がる。全員があいさつをしたあと、小松さんがギターを持った。安田川の歌や「追い風ヨーソロ」のテーマソング、そして名曲「東京にいる君に」を次々歌ってミニライブ。最後は小松健太さんが秀吉さんに送った「大心劇場の歌」を健太さん自ら舞台で歌った。フィナーレまでいた観客(有料入場者)は31人。その人たちに向かい、秀吉さんはこう頭を下げた。「劇場70年、いい思い出ができました。ありがとう!」。両日合わせた有料入場者数は110人だった。