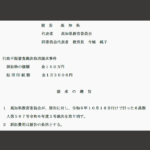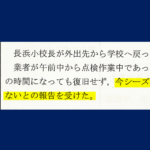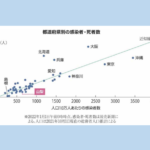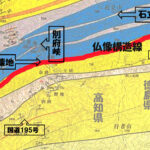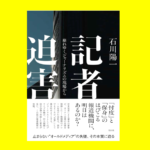2025年8月6日、原子爆弾の惨禍から80年を迎える広島。高齢になった被爆者の声を今、第二、第三、第四世代が受け継ぎ、内外の来訪者に語り続けている。「あの日」だけでなく、それからの苦しみをどう生きたかを伝え、広島との人生の出会いを見つけてもらう―。当事者の母親と共に「平和のための通訳」をする小倉史郎さん(58)、新しい「体験と学び」の場づくりをする久保田涼子さん(42)に継承の意味を聴いた。 (寺島英弥)
ー久保田さんは「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展」の代表です(『』には人それぞれの広島への思いが入る)。広島と東京を行き来してウェブのデザイナー、クリエイター育成スクール「デジタルハリウッドSTUDIO広島」を経営しながら活動しています。
久保田 「継ぐ展」は、戦争を知らない世代が被爆地広島との出合いの体験を通して歴史や記憶、人の思いをどう継いでいくかを考える企画展です。契機は、仕事をしていた東京で『父と暮らせば』(被爆後の広島を舞台にした井上ひさしの戯曲)の朗読劇を稽古していた俳優さん二人から、広島弁の指導をお願いされたこと。広島を学び伝えようとする熱い思いに心を動かされて。私は子どものころから平和学習を受けてきましたが、30代になって、あらためて自分の意思で平和資料館などを巡り、被爆体験をした祖母(2021年に94歳で他界)らの話に初めて耳を傾けました。知らなかったことを学び直し、何ができるのかを考えました。被爆70年に当たる2015年に第1回「継ぐ展」を開こうとした際、被爆二世から「被爆70年だからやるの? 誰のためにやるの?」と問われ、毎年できることを続けています。第一世代は生々しい死と生の傷みを語りましたが、三世の私たちができることはデジタルツールも取り入れながら、当事者の思いと広島を五感で体験してもらう、未来につなぐ場づくり。小中高生の参加が増えています。
-1024x768.jpg)
「あの日」から80年を迎える広島市の平和記念公園。年200万人以上が内外から訪れる=2025年6月8日
ーどんな活動をしているのか、一端を紹介してください。
久保田 現在特に力を入れて取り組んでいるのが、広島を訪れる修学旅行生向けの平和学習ツール「ピースパズル」。ワークシートとスマホを使うデジタルスタンプラリーを組み合わせた参加型の学習ツールです。私たちが大学と一緒に開発しました。平和記念公園を中心に慰霊碑や被爆遺構を巡り、ボランティアスタッフが出題する問いに答えながら、そこであった出来事を勉強してゆく。人と触れ合う「余白の時間」が生まれ、質問を受けるスタッフにも学びの機会になります。県外出身者が多い広島大学では1年生たちに毎年「ひろしま平和共生リーダー概論」の講義をしています。自分たちの考えるピースパズルを企画してもらい、身近でできる平和アクションを議論します。受講した学生がボランティアに参加してくれることもあります。全国各地の学校と広島をつなぐオンライン平和学習や、多世代が参加するワークショップ、被爆者や平和活動者へのインタビューを日本語と英語のウェブサイトで発信する活動も続けています。

広島市内の小学校を訪ね、教室で子どもたちに語り掛ける久保田涼子さん=2024年9月(提供写真)
ー小倉さんはお母さんが体験者の二世ですね。
はい。私は広島を離れていた年月が長かった。大学、就職が東京で、転勤先の神戸で阪神淡路大震災(1995年1月17日)に遭遇し、「何が神戸でできるか」と悩むうちに神奈川へまた転勤し、心を引き裂かれるように悩んだ。その思いがあって、東日本大震災(2011年3月11日)が起きると、宮城県南三陸町、石巻市、岩手県陸前高田市などに2015年までボランティア活動に通いました。広島に帰郷したのは20年。平和の活動をしていた両親と初めて向き合えました。母の桂子(88)は8歳の時、爆心から2.4キロの場所で被爆しました。父馨(かおる)は米国生まれで、戦争前に広島に帰って出征先で敗戦を迎え、戦後に広島市職員に。英語を生かして国際平和都市づくりに尽力し、広島平和記念資料館の館長を務め、平和宣言の起草にも携わっています。1979年に58歳で他界した後、父の友人の作家ロベルト・ユンク=原爆と科学者たちを追った『千の太陽よりも明るく』(邦訳)の作者=から母が、広島での記者会見で通訳を依頼されました。通訳は未経験でしたが、「被爆者の苦しみを見てきたあなたこそ広島を伝える通訳にふさわしい」と励まされ、英語を猛勉強して通訳の道を歩みました。1984年には「平和のためのヒロシマ通訳者グループ(HIP)」を立ち上げ、私も帰郷後にメンバーとなっています。
と史郎さん=2022年9月提供写真-1024x768.jpg)
米国のアイダホ大学に講演に招かれた小倉桂子さん(左)と史郎さん=2022年9月(提供写真)
ー半世紀、広島を離れて人生を歩んだ後、平和の活動に参加したのはなぜですか?
小倉 子どものころに受けた平和教育は、重苦しく、受け継ぐには覚悟とエネルギーが要り、私は遠ざかりました。転機は、私が大好きだった神戸が震災に遭ったこと、そして東北の被災地を歩いて呆然としたこと。津波で破壊された町々が、被爆後の広島のパノラマ写真と同じように映りました。ふるさと、家族を失うことは、自分の皮膚をべりべりと引きはがされるような傷みだったはずです。そこからどうやって立ち直っていったのか。原爆は人と人の間に差別も生みました。体験者の悲しみ苦しみを自分はどう伝えられるだろうと悩み、被爆から復興への歴史を勉強しました。母の活動に初めて触れたのは2022年の9月です。講演に招かれた米国のアイダホ大学に同行し、大勢の聴衆に英語で語りかける母の話に聴き入りました。
<講演で桂子さんは被爆者たちの悲惨な姿を語り、「将来の核戦争に、皆さんは関わってほしくない。どうかどうか、一緒に考えてください」と訴えた。2023年のG7広島サミットでは平和記念館資料館を訪れた各国首脳の通訳をし、2024年12月にノルウェーのオスロで開かれたノーベル平和賞の記念フォーラムには受賞した日本被団協に同行、核廃絶を訴える被団協を見守った>
ー久保田さんも「継ぐ展」の活動で桂子さんをインタビューしていますね(同上ウェブサイトの『語り継ぐ 19回』)。そこにあった「私は8歳の時に被爆していますが、被爆者への差別を恐れて、原爆に遭ったことは誰にも言うまいと心に決めていました 」という言葉にショックを受けました。
久保田 被爆者の中には、原爆のことを語りたがらない方が多くおられます。悲惨な出来事を思い出したくなかったり、広島出身者というだけで差別をされたり、結婚ができなかったり、と理由はさまざま。ただ、私が活動を始めた戦後70年の頃から、ようやく語り始めた人たちもいます。被爆者を家族にもつ人たちが、その思いを受け継いで、次の世代に伝えていこうと動き始めている姿も見てきました。最近知り合った長崎出身の二十歳の大学生に活動のきっかけを尋ねると、受け身で平和学習を聴いていた時は意識しなかったのに、自分のルーツに関心を持ったことが「気づき」になったそうです。
小倉 私は子どものころ、父がいる平和記念資料館の館長室に入ったことがあるし、母が「公人」として通訳の仕事をしている姿も見ていました。母と一緒にアイダホ大学へ行った時、テレビの取材者から「跡を継ぐのですか?」と問われましたが、それまで母は被爆の体験を直に話してくれたことはなかったのです。私は東北の被災地で余震に脅えながらボランティアの活動をしましたが、あまりに激しい、つらい悲しい体験をした人はトラウマ(心の傷)に苦しみます。被爆の体験者たちは「あの日」だけでなく「それから」の苦しみも背負って生きてきました。母は広島を訪れる多くの外国人に、そして海外でも、そのことを語ってきた。それが核兵器の恐ろしさだということを、私も広島で平和を願う通訳の一人として伝えていきたい。 (㊦に続く)