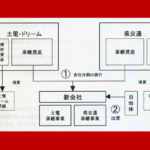山あいにあるその棚田に通い始めて14年になる。河野豊さん(76)は、松山市在住の棚田写真家だ。撮影の舞台は大洲市長浜町戒川の壺神山裾野に広がる「天空の隠れ里」樫谷棚田。ことしの春から夏にかけて、河野さんらの「樫谷棚田保存会」が発足10周年記念イベントを計画している。「棚田オーナー・トラスト制度」導入など、これまでの道のりを振り返るのだ。そこには、走り続けた長い年月の重みが集約されている。(西原博之)

里山に立つ河野豊さん
人の生活があってこそ棚田がある
棚田に惹かれたのは30年近く前だった。山里の写真を撮影するために南予の棚田を訪れた。何枚か写真を撮った。しかし何か足りない、違和感をぬぐえない。思い切って棚田の手入れをしている人に話しかけた。だが重い口は開かない。翌日、また訪れる。なかなか打ち解けてくれない。それでも山へ入る。毎日、毎日。少しずつ気持ちが通い始めた。が、「まだシャッターは押せないんです」。心を開いてくれ、自然に会話ができた時、河野さんの中でやっと、棚田と、それを守り手入れしながら中山間地に生きる「守り人」が一体化した。納得してシャッターを切った。自分の思い描いてきた棚田の風景が、そこにあった。
棚田は、狭隘な山間地で稲作を可能にした先人たちの知恵の結晶だ。斜面を拓き、畔(あぜ)を築き、水を張り、猫の額のようなスペースに苗を植える。そして収穫を喜ぶ。何百年も続いてきた山里の営みだ。だからこそ、人の生活を切り離して棚田は存在しえない。
誰しも感銘を受ける美しさだ。ただ、美田に惹かれてシャッターを押しても、それは絵葉書のような風景写真でしかない。「そこに生きる人の息遣いや苦労、棚田に向ける思いを理解しないと本当の棚田の姿は切り取れないんです」。河野さんの写真にはだから、人々が棚田を拓き、守り、手入れを続けてきた歴史と生活が織り込まれている。画面自体に守り人が写っていなくても、人の営みが鮮やかに伝わってくる。
里山というのは人工的な自然だ。奥山には手つかずの自然があり、里には人の生活がある。山の端を利用しながら雑木林をつくり、落ち葉を拾い、肥やしにし、人々は営々と里山を築いてきた。棚田はその象徴だ。山と人の生活を穏やかに緩衝させるバッファゾーンともいわれる。緩衝地帯であるからこそ、山と里を穏やかにつなぐ。多くの生き物が棲み、生物多様性の維持には欠かせない。地すべりを防ぎ、国土保全にも有効だ。水源涵養の役目も大きい。生産の場であると同時に、多様な機能を備えているのだ。人は棚田と、その背景にある雑木林を生活圏に、野生動物とも共存してきた。日本の自然と風景は、そうして成り立ってきた。

田植え後の樫谷棚田。整然と植えられた苗が美しい=河野さん撮影
「なんでこんなに苦労して」
河野さんは西予市野村町の中山間地で生まれた。幼いころからそこには茅葺き屋根があり、里山があった。男4人兄弟の末っ子。だから「家」にしばられない。大学で「民俗学」に出合った。里山を撮り続ける河野さんの心に支柱としてあるのが民俗学だ。若いころから茅葺き民家などの写真をよく撮ってまわった。歳月とともに失われる「形あるものへの想い」を写し残しておきたい。そう思ってシャッターを押し続けた。里山のシンボルである棚田との出会いは、必然だった。
今も毎日のように県内外の棚田へ通う。前年まで生き生きと水が張られていた棚田が翌年には荒廃している現実を、あちこちで目の当たりにしてきた。高齢化の波はまず山里に押し寄せる。平地の水田に比べ、棚田の維持と管理と耕作は数倍の労力と時間を要する。高齢者にはつらい作業だ。「なんでこんなに苦労して米をつくらんといけんのじゃろか」と年老いた婦人がつぶやくのを何度も聞いた。代掻きにはじまり田植え、浮稲の見回り、稲刈り、稲わたし、稲木づくり。機械が入らない棚田ではすべてが手作業だ。河野さんはその歴史をつぶさに見てきた。想像を絶する困難が伴うが、この歴史を途絶えさせないためにあらゆる手段を駆使したいと考えている。
緊急の課題は樫谷棚田の保全だ。壺神山の西山麓に広がる約3ヘクタール・257枚。標高は470~520mにわたり、7戸の農家が耕作に当たっている。樫谷がある戒川地区は49世帯で86人。樫谷は3世帯8人の集落だ。高齢化で人口減が止まらず、2013年には戒川小学校が廃校となった。樫谷棚田周辺ではシキミの栽培もほそぼそと行われているが、これも存続が危うい。河野さんの危機感は募る。
「棚田の保全は日本の里山、環境の保全にもつながるのです」と河野さん。保全の手段としてまず取り組んだのは、とにかく棚田を知ってもらうことだった。2010年、撮りだめた写真を収めた写真集「南伊予の地域遺産棚田-写しだされた原風景」を出す。そこにある樫谷棚田の写真を目にしたのが棚田学会顧問の中島峰広さんだった。中島さんは2012年に愛媛県を訪れ、河野さんの案内で樫谷棚田を訪れる。それをきっかけにできたのが「樫谷棚田保存会」だ。2015年には「棚田オーナー制度」がスタートし、毎年20~30組の家族や団体が田植祭や収穫祭に参加し、棚田に触れるようになった。樫谷棚田の保全運動は今も広がりつつある。
.jpg)
樫谷棚田で稲木をつくる「守り人」。こんな風景も失われつつある(河野さん撮影)
棚田を支える地域が国土と水を守る
河野さんの活動は全国で評価され、2018年には「棚田学会賞」を受賞した。河野さんにとってはそれも棚田保全の一つの手段だ。高齢化の波は止められない。若者の定住や後継は、さらに難しい。だから、オーナー制度を通して若い夫婦や子供たちに棚田が存在する意義を理解してもらいたい。さらにその子や孫に棚田の物語を語り継ぐことができるかどうか、河野さんは常に考えている。棚田が単なる生産の場ではないこと。戦前から戦後にかけて、ひもじさをこらえ、食料確保のために地をはいつくばって開墾したのが棚田であること。ぎりぎり生きてゆくための知恵であったこと。
未来を見据えれば、さらに構想は膨らむ。「棚田だけをピンポイントでアピールするのではなく、集落、地域、自治体まで広げた面として捉えることが大事」だと河野さんは言う。棚田の多くは限界集落に位置する。限界集落を維持するためには、そこに至るまでの道路や支援する地域、人が必要だ。棚田があり、それを支える地域があるから国土は守られ、水は豊かに流れる。その意味を、町の人にもわかってほしい。点から線へ、面へ。河野さんの取り組みは地道だ。しかし、「やらねば」と思っている。
河野さんは最近、これまでやってきた活動を振り返ることがある。このままで棚田を、里山を後世に残せるのか、と不安に駆られることもある。棚田は個人の私有物だが、国民共有の貴重な財産でもある。だから、「維持する苦悩でなく、活かす希望を考え」ながら走り続けるしかないと思う。
.jpg)
黄金色に実った棚田の稲。刈り取りを待つのみだ=河野さん撮影
棚田写真展に3日間で400人
樫谷棚田保存会の10周年を記念し、2月23日から3日間、大洲市東大洲のオズメッセで棚田写真展が開かれた。棚田の魅力をアピールするため大きく引き伸ばされた写真20点を展示。会場には3日間で約400人が訪れ、臨場感あふれる四季折々の棚田の表情に触れながら、保存の重要性について理解を深めた。河野さんは、これまでの歴史を振り返りつつ来場者に「保存するために協力をお願いしたい」と話し、棚田の重要性をアピールした。3月には棚田参観日、5月には田植え体験会を計画中。

棚田の写真を前に、その魅力と保存への協力を呼び掛ける河野さん=2月23日