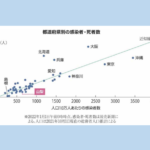ラジオ沖縄の記者やディレクターを長く務めた源啓美さん(76)が4月末、高知市を訪れていた。カツオ漁が盛んだった沖縄・渡嘉敷島の出身で、カツオ船の機関長だった祖父は1944(昭和19)年10月10日、日本軍に徴用されて沖を哨戒していたときに米軍の機銃掃射で死亡。母親は激戦の沖縄本島南部を軍とともに移動、摩文仁の崖から海に身を投じて自決(未遂)を図っている。源さん本人は高校卒業後、米軍統治下の1967(昭和42)年から記者を務めてきた。数多くの現場経験が、言葉の一つ一つに沖縄の歴史を凝縮させている。(依光隆明)

ラジオ沖縄での日々を話す源啓美さん(高知市内)
「正しい日本語を使いましょう」
2カ月前の2024年2月に99歳で亡くなった女性史研究家でジャーナリスト、もろさわようこさんの「お別れ会」に参加するために来高した。長野県生まれのもろさわさんは、長野、高知、沖縄、神奈川に拠点を持って活動していた。源さんは50年前にもろさわさんと知り合い、昨年8月には信濃毎日新聞記者の河原千春さんと共同編集で『沖縄ともろさわようこ―女性解放の原点を求めて』を上梓している。その中には20年前に発表した祖父や母・芳子さんの話も再録されている。
源さんは1948(昭和23)年1月に渡嘉敷島で生まれ、渡嘉敷島で育った。小学5年のときに両親が沖縄本島へ働きに出たため祖母と暮らす。日本の歴史とは異なる歴史を歩んできただけに、沖縄は独特の言葉を持っている。それを直そうと、学校では教師たちが「正しい日本語を使いましょう」と言っていた。
「私たちの時代でも方言札(地元の言葉を話してしまったとき、ペナルティーとして首からぶら下げさせられた札)の名残はありました。大人たちが話すのは沖縄の言葉です。子どもに向かって正しい日本語を話そうとするが、いわゆる正しい日本語ではなかった」
中学3年で両親の元に行き、沖縄本島の中学校から普天間高校に進んだ。
1963(昭和38)年に入学する。米軍普天間基地のすぐ北にある高校だった。すぐそばにある基地を意識することはなかった。
あるとき国語の教師が源さんにこう声をかけた。「ヒロミ、お前はかわいそうな奴やなあ」。「どうして?」と聞く源さんに、こう言った。「沖縄の言葉を使えない」。社会科の先生は米国で起きたマッカーシズム(赤狩り。文化人や科学者に共産主義者の疑いをかけ、オッペンハイマーやチャップリンら多くの人々を迫害、追放した)のことに触れ、その中でメディアがどう抑圧され、マスコミ人がどう戦ったかを話してくれた。先生の話に刺激を受け、新聞記者になりたいと思った。

河原千春さんと編集した『沖縄ともろさわようこ』
19歳でラジオ沖縄報道部に
中学3年で放送委員となり、高校では放送部に入った。放送部長となった高校2年のとき、全国高校ラジオ放送コンクールに参加した。1位不在の2位に入り、メディアにも取り上げられた。出品したのは「アホウドリの子」と名付けたラジオ劇だ。アホウドリは自分の卵を他の鳥の巣に産んで育てさせる。それを日本と沖縄の関係にオーバーラップさせた。
「脚本を書いてくれたのは3年生の男の子でした。その男子は卒業前に自死しました。高い問題意識を持った人でした」
高校3年になり、大学に行こうとして失敗する。米軍占領下だったが、日本の大学へは国費・自費沖縄学生制度という道が開けていた。沖縄の中で選抜試験を行い、優秀な生徒を日本の大学に割り振って留学させるのである。源さんはその試験に失敗し、琉球大の入学試験にも落ちてしまう。浪人を決めたものの、アルバイトが欠かせない。
浪人していた秋に転機が訪れた。
「ラジオ沖縄が受付のバイトを募集していたんです。応募したら、『受付は社員でやることに決まった。でも報道部の庶務係だった女性が辞めたので、よかったら報道部に入らないか』と言われたんです」
秋に面接を受け、社員で採用されて報道部に所属した。勤務のスタートは1月から。19歳になったばかりだった。
「面白かった。記者たちが現場から電話で記事を送ってきて、それをリライトするんです。共同通信や毎日新聞の原稿は電報で届いて、それもリライトします。仕事をするうち、自然と沖縄の状況が勉強できました」

沖縄の自然は美しい(南城市の奥武島)
B52墜落や「燃える井戸」
沖縄の日本への復帰(沖縄返還)は1972(昭和47)年。復帰前の沖縄の日々を、ニュースをリライトしながら知っていく。文章の指南役は戦前からの新聞記者だった1919(大正8)年生まれの徳田安周。源さんの文章を添削し、文章教育をしてくれた。
読谷村出身の徳田は早稲田大学を出たあと沖縄で新聞記者となり、1942(昭和17)年には陸軍の一兵卒として南鳥島に出征している。復員したあと沖縄に戻り、琉球新報からラジオ沖縄に転じていた。文化人として著名で、『沖縄てんやわんや 気楽に読める沖縄の世相風俗史』『天命に生きる 上江洲文子波乱万丈の半生』『おきなわ千一夜 物語沖縄風俗史』などの著書がある。
当時の記者には酒呑みが多かった。職場で夕方から酒を飲むのがいるし、居酒屋では酒と激論が飛び交った。十代の源もその中に入った。酒もけっこう飲めた。家まで帰るタクシー代がもったいないので閉店まで居酒屋にいて、そのあと深夜喫茶に移って夜を明かすこともたびたび。源さんが言う。
「先輩に恵まれてジャーナリストへのあこがれが満たされていきました。記者と一緒に現場に行くこともありました。嘉手納のジェット機墜落や『燃える井戸』の現場にも立ち会いました」
嘉手納の話は、1968(昭和43)年11月に嘉手納基地内で起きた米空軍の大型爆撃機B52墜落事故。ベトナムの作戦に向かうため爆弾を満載したB52が離陸に失敗、大爆発を起こした。近隣住民16人が負傷したほか365棟の建物が被害を受けている。「燃える井戸」は嘉手納基地の航空燃料が地下に流出し、地下水に混じった事件。住民が使っている井戸の水が燃えたのである。1967年に発覚し、米軍が流出を認めなかったこともあって解決まで時間がかかった。

ラジオ沖縄に入ったころを振り返る源啓美さん(高知市内)
おさげ髪と高校スカート
復帰前の沖縄は、激動の日々だった。夢中になって仕事をした。「大学受験なんてどこに行ったか分からない」と笑う。やがて一人で取材に出るようになった。源さんは身長145センチの小柄。しかも三つ編みのおさげ髪で、白いシャツにスカートは高校の制服だった。どう見ても記者には見えない。というより高校生だった。取材に行くと「あとで男の人が来るんですよね?」と聞かれることもあった。「行く先々で子ども扱いでした」とまた笑う。
テレビと違ってラジオにカメラマンは要らない。だから一人でも行けたのだが、今と違って機材は大きくて重かった。
「こんな大きなデンスケ(取材用可搬型テープレコーダー)を肩にかけて。重かった。肩に血が滲んでいました」
当時、沖縄の記者には仲間意識があった。
「今は『敵さん』とか言うけど、当時は全然違って。他社が記者会見に間に合わなかったら、うちの素材を提供していました。ごく普通にです。『これは沖縄のためだから』が共通認識でした」
後年、トラブルになったこともあった。
「OHK(NHKのこと)に音を貸したらNHKのものになってしまって。コザ騒動の音声なんですけど、NHKのものになって、『NHK提供』でいろいろなものに使われてしまっているんです。当時、音を録った仲間がその経緯を琉球新報に書きました。映画に『NHK提供』で使われて、抗議したけれどNHKが聞く耳持たなかったんです」
(補記・「コザ騒動」等の音源について、NHKは2022年からラジオ沖縄の許可を得て権利処理をしていることが掲載後に分かりました。2020年に琉球新報がこの件を報じたことがきっかけで、NHKがラジオ沖縄に著作権があることを認めたそうです。2022年の沖縄復帰50年の特番から「音源ラジオ沖縄提供」の表記を入れているそうです)
コザ騒動(コザ暴動)は1970(昭和45)年に起きたコザ市(現沖縄市)での騒乱事件。度重なる米軍機墜落や米兵による犯罪など、司法権、警察権を米軍に握られる米軍施政下の不満が人身交通事故をきっかけに暴発した。翌71年に米軍は沖縄に隠していた毒ガスの搬出を行うが、源さんはそれを記者レポートしている。
「ラジオカーで行ってリポートするんです。アナウンサーは徹底的に訛り(なまり)を直されますが、記者はそうでもありませんでした」
沖縄の日本復帰に記者で立ち会ったあと、復帰から2年ほどして営業部(編成部)に移る。
「ラジオの営業というのはコピーライターなんです。それを9年やって、1980年代の初めに制作に移りました」

焼失前の首里城の展示から。沖縄は独特の文化を育んできた
「女たちの電波ジャック」
ラジオ沖縄の社員数は約80人。ラジオ単営の小さな局だが、ローカルに徹しながらほとんどの番組を自社制作していた。
「厚生、教育を担当して、売春防止法や婦人会活動の番組を作りました」
高校時代の先生の影響もあり、沖縄の言葉にはこだわりを持っていた。
「沖縄の言葉を日本の言葉に直さないといけないのですが、私は沖縄の日常の言葉にこだわったんです。沖縄の日常の言葉を使って料理番組をしていた料理研究家の方が他局の番組をやめさせられて『ラジオ沖縄でできないか』と言ってきたことがあって。『いつもの言葉(沖縄の言葉)でやりたいのですが、いいですか?』『いいですよ』と。その番組が大人気となって、ウチナーヤマトグチ(沖縄訛りの日本語)が公に認められるきっかけになりました。若者に支持されたんです」
「正しい日本語」の教育に熱心だった土地柄だけに、反発もあった。源さんはある女性から抗議の電話をもらう。「放送局が正しい日本語を使わないのは問題だ」と。その女性は「自分の夫はNHKだ」と話していた。
その後も源さんは積極的に沖縄の言葉を使う。
「言葉は自分の生活そのものです。言葉を否定されるのは生活を否定されることです。使っている言葉が公に求められないのはおかしい、直す必要はない、と思っていました」
高校時代までは「正しい日本語」しか話してはいけなかった。そのことへの疑問が、身近な生活の言葉に目を向けた。
「コマーシャルも沖縄と日本の言葉をごっちゃにして使った」と源さんは振り返る。自分たちの活動やタイトルには意識してゆいまーる(助け合い)などの沖縄言葉を使った。そのひとつが「うない」である。
「女きょうだいという意味ですが、男きょうだいからの呼び方です。女きょうだいから男きょうだいを呼ぶときは『うぃきー』で、続けて言うときには必ず『うない』を先に言います。男性と対等、平等に扱われる社会を目指して『うない』を使いました」
1985(昭和60)年、源さんは沖縄の問題を女性目線から捉えるイベント「うないフェスティバル」を企画する。
「ラジオ沖縄の開局25周年記念でやりました。『ナイロビ会議の女性版をやろう、女性たちの文化祭だ』と。沖縄の女性たちとラジオ沖縄、那覇市の共催です」
ナイロビ会議はその年、ケニアのナイロビで行われた国連の「世界女性会議」のこと。世界中で女性の活動に目が向き始めていた。
「行政とメディアと女性たちが一体となってやりました。それをラジオ沖縄は12時間の生放送で報じました。沢地久枝さんに講演をしてもらいましたが、それもそのまま生放送しました。当時、リベラルな人の発言をそのまま電波に乗せるなんてありえなかった。『女たちの電波ジャック』なんて言われました」
女たちの電波ジャックは高く評価され、源さんは日本婦人放送者懇談会賞(現放送ウーマン賞)や年間最優秀プロデューサー賞を受賞する。

焼失前の首里城の展示から
人をつなげた「女性ジャーナル」
沢地さんら全国各地の女性とつながりを作ったのは源さんの番組だった。
「ワイド番組の中に『女性ジャーナル』というコーナーを作っていたんです。先進的な活動をしている女性たちを、県内はもちろん県外の人でも電話で出演してもらうんです」
ラジオは声だけだから電話でつなげば出演できる。電話さえつなげば世界中の誰だって出演を頼むことができた。源さんがインタビューし、それを生で電波に乗せた。
「いろんな女性を取り上げました。沢地さんもそうだし、女性初の重機の運転手さんや、大阪の女性の大工さん2人も取り上げました。大工さんの1人は済州島出身の在日の方で、のちに沖縄へ移住しました。もう亡くなられましたが。女性ジャーナルはタイトルを代えながら1983年から30年くらいやりました」
沖縄は台風の通り道に当たるのでラジオは必需品だった。戦後早い時期から役場に親ラジオがあり、各家庭には有線で受信する端末があった。トランジスタラジオが普及すると、畑にも市場にもラジオが持ち込まれた。
「うないフェスティバルをみんな市場とかで聞いていました」と源さん。1960年代の半ば、東京オリンピックのころからテレビも普及したが、ラジオを聞く人も少なくなかった。民放ラジオ(中波)は今でも沖縄に2つ。沖縄タイムス系の琉球放送が先にできて、そのあとに続いたのが琉球新報系のラジオ沖縄だった。

仲間たちと作った米軍+自衛隊基地の地図を手にする源啓美さん。「米軍と自衛隊の基地を1枚の地図にしたのは意外とないんです」
自費で取材し、一人で編集
高校生のように見られていた新米記者は、いつの間にかベテランになっていた。
ディレクターとして自由に番組を作ることができるようになったが、アシスタントディレクターはつけてもらえなかった。
午前7時から正午まで「生ワイド」を担当し、お昼で正規の仕事が終わる。それからが自分の仕事だった。取材に行き、編集する。アシスタントディレクターがいないのでヘッドホンはつけっぱなし。編集作業も一人でやった。音を聞かないと編集できないので、編集には時間がかかる。朝から夜まで働いた。
ハードワークの代償と言えばいいか、番組作りに自分の意見を通すことはできるようになった。
「会社が『やれ』と言う番組はスポンサーがついている番組。(自分がやるような)堅苦しい番組にはスポンサーがつかない。でもつかなくてよかったと思う。じゃあどうするかと考えて、自分たちでスポンサーを探したり、女性たちが自らスポンサーになったりした」
環境問題の番組を作り、女性問題の番組も作った。
「『これは(この番組は)お前が勝手にやってるんだろ、運動なのか仕事なのか分からない』なんて言われながら。わがままを許してもらっていました」
自費で取材することも少なくなかった。たとえば1995(平成7)年に中国・北京で行われた第4回世界女性会議も自費で取材し、放送した。ほか、1987年(昭和62)には持続可能なツーリズムの在り方を学びにタイへ、1990(平成2)年には環境先進国のドイツ、スウェーデンへ、1996(平成8)年には米軍の少女レイプ事件に抗議する女性たちの米国ピースキャラバンに、いずれもメンバーのひとりとして自費参加して取材、放送した。一人で考え、自費で取材し、一人で編集して放送する。これもハードワークだった。
「膨大な録音データの中で、番組に使えるのは10分の1もない。編集作業を続けて耳を悪くしました。難聴です」
自らを「つなぎ役」と表現する。「女性たちが結束するつなぎ役をやっている」と。女性ジャーナルでいろいろな女性とつながり、それらの人々を結びつけてきた。1985年に「うないフェスティバル」を始めたあと、1995年に発足した「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」の事務局長を務めている。沖縄9条連の共同代表でもある。
自分の人生を「非常に得をしたなあと思う」と振り返る。「自分自身が問題として抱えていることを明らかにしたいとき、メディアとして行ける、普通なら会えない人にも会える」と。そうやって多くの人に会い、結び付けてきた。

那覇の街。人口32万人
古里渡嘉敷島を見つめ続ける
入社したころ、取材に行くときには運転手も技術者もアナウンサーも一緒だった。しかしそんな時代は長く続かなかった。「どんどん人が少なくなって。アナウンサーの私有車で、ガソリン代だけ会社が出して行くようになり、最後は『2人分は残業代出せないから1人で行け』となりました」。
60歳で定年退職したあともラジオ沖縄で番組作りを続けてきた。完全に引退したのはことしの3月。19歳のときから57年間にわたってラジオに関わり続けてきたことになる。
最後の仕事を終えた3月26日、源さんは自身のブログ「うちなぁ かな日記」に「57年間の仕事人生を卒業しました!」と題してこう書いた。
「沖縄の祖国復帰を挟んでの57年間、嘉手納B52墜落事故も、燃える井戸も、コザ騒動も、毒ガス移送も、復帰の朝も、交通方法変更も、通貨切り替えも、日中国交回復も、若夏国体も、国際女性北京会議も、少女強姦事件も、現場に立ち激動の沖縄を見つめ続けてきた。この仕事だったから、今の私がある、と言っても過言ではない」
出身地の慶良間諸島・渡嘉敷島は集団自決や軍隊慰安所でも知られている。盛んだったカツオ産業は米軍基地の影響で廃れた。
「戦後、米軍のミサイル基地ができたんです。基地建設は日銭が入るでしょう。カツオ漁は給料が入るのが1年に1度ですからね。しかも基地関連の方が給料もいいので、若者がカツオ漁から米軍基地に流れたんです。カツオ節工場はつぶれちゃった。三つもあったのに」
ミサイル基地は1960(昭和35)年から建設に入り、62年に完成する。7年後の69年には閉鎖となった。
「基地が撤去されてもカツオ漁は再興できませんでした。渡嘉敷島はいろんな問題が凝縮して起きている、沖縄問題の縮図のようなところです。私、渡嘉敷島の平和学習ツアーの案内もしているんですよ。5月半ばには高知の平和運動センターの皆さんを案内する予定です」
祖父までは古波蔵(こはぐら)姓だった。源姓になったのは父親の時代からで、父方の叔母が「源為朝の流れをくむ家系だから源姓に戻るべきだ」と主張したらしい。沖縄は戦争で戸籍が焼失し、新たに戸籍を作成したことが背景にあった可能性もある。源さんは生まれたときから源姓。
琉球舞踊歴は50年に達し、琉球新報古典芸能コンクールで最高賞を受賞した。